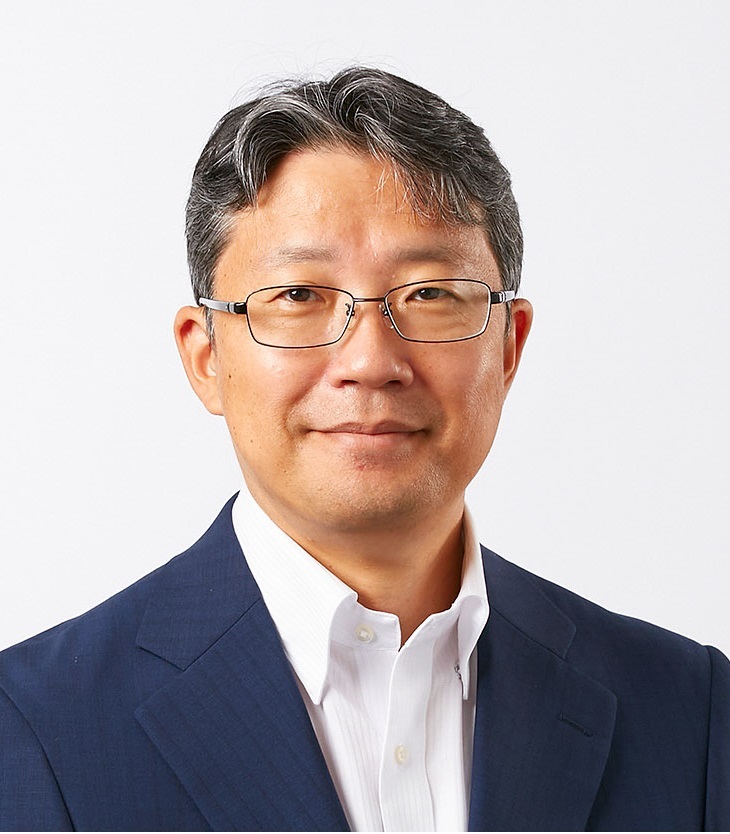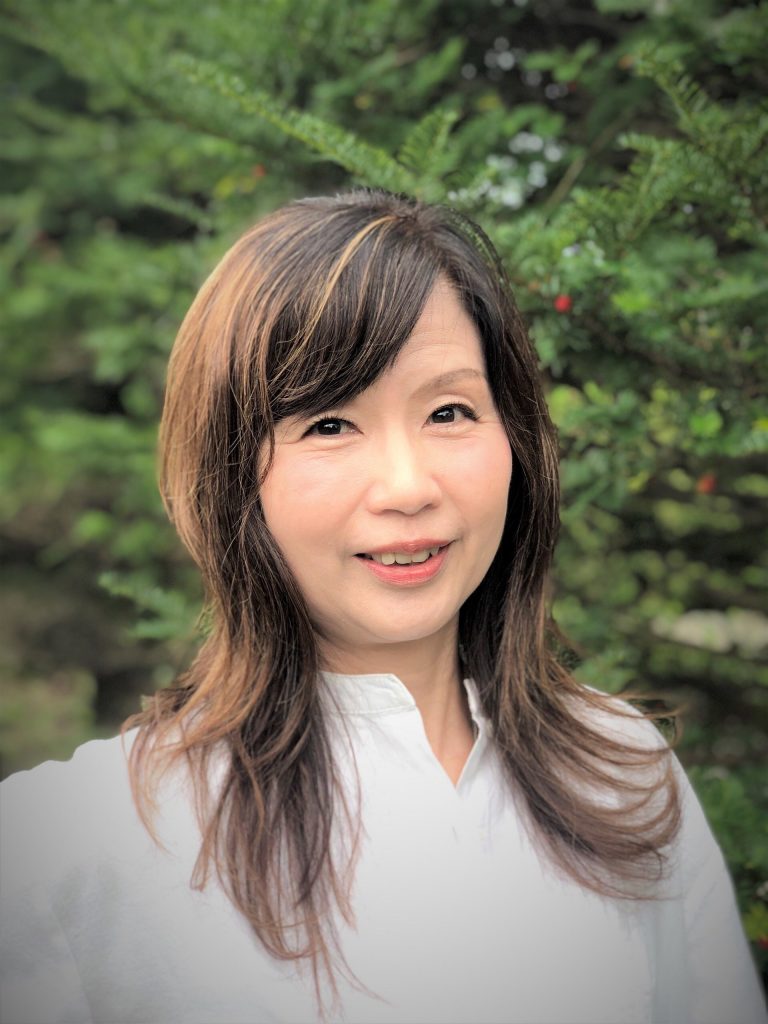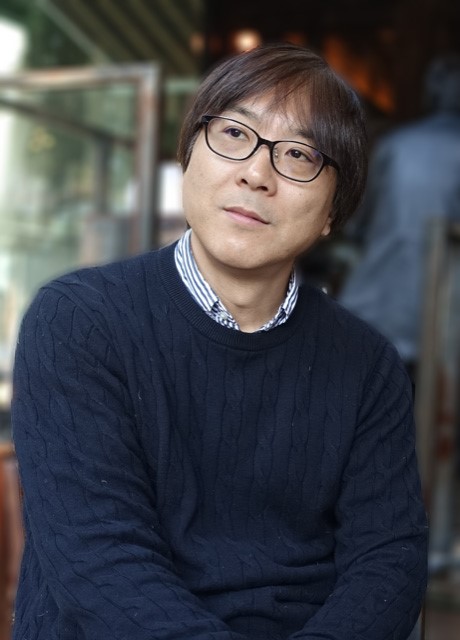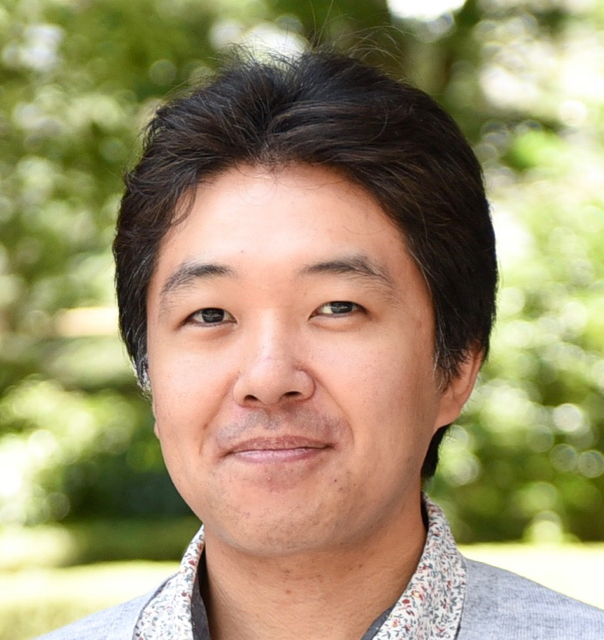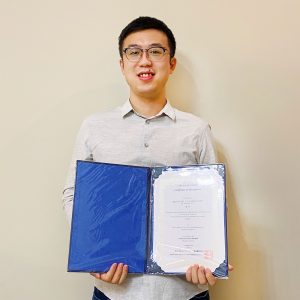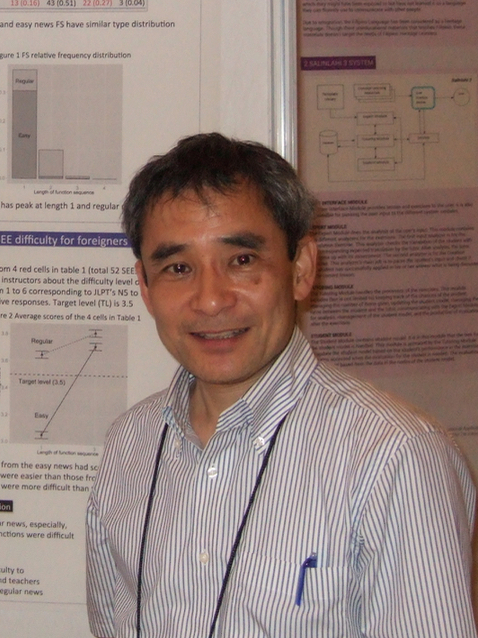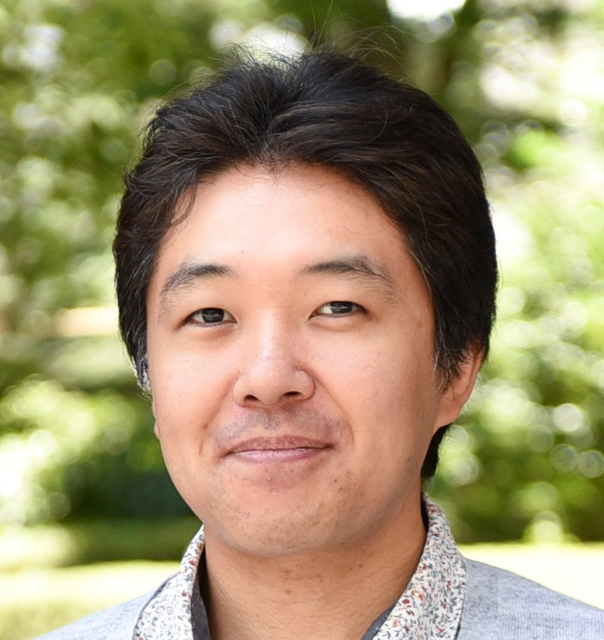『機械翻訳』を訳した翻訳者が考えていること
高橋聡
個人翻訳者(日本翻訳連盟・副会長)
「機械翻訳」とは何か? どこから来て、どこへいくのか?
これは、2020年9月に刊行された拙訳書『機械翻訳 歴史・技術・産業』(ティエリー・ポイボー[著]、中澤敏明[解説]、高橋聡[翻訳])の帯に、出版元である森北出版の担当編集者が付けてくれたキャッチコピーである。そして、日本翻訳連盟(JTF)が今年4月、創立40周年を記念して開催した第1回関西セミナーのタイトルにも、このフレーズを使わせていただいた。
なお、この訳書については、『AAMT Journal』No.74で、立教大学の山田優先生が、実に詳しい書評を書いてくださった。解説と論評は、さすが専門家と唸ってしまう鋭さで、ありがたいことに私の翻訳にも言及してくださっている。この場を借りて、心よりお礼の言葉をお伝えしたい。
さて、冒頭のキャッチコピーは、現在の翻訳業界が機械翻訳を捉えるヒントとして実に的確だったと思う。そこで、以下ではこのコピーをもとにして、いち個人翻訳者がいま機械翻訳について考えていることを綴ってみたい。
● 機械翻訳とは何か?
手前味噌で恐縮ながら、この問いの答えを本書はとてもコンサイスにまとめている。いろいろな機械翻訳技術のしくみと歴史、それが必要になった理由と開発の経緯が時代ごとに整理されており、さらに産業としての現状まで述べられている。類書のなかでも初めてではないだろうか。しくみを知れば、おのずと限界もはっきりする。技術的(数学的)に難解な要素はできるだけ省いてあるので、業界関係者には、このくらいのレベルで機械翻訳の概要を抑えていてほしい。その土台があって初めて議論が成り立つ。
● 機械翻訳はどこから来たのか?
特に同業者、つまり翻訳者や通訳者にいちばん知っていただきたいのはこの点だ。「翻訳」というものを考えるとき、ヨーロッパ(中近東までを含む)と日本では、ベースとなる地理的・文化的・言語的土壌があまりにも違う。
ヨーロッパは、いわば"翻訳の本場"だ。複数の民族、複数の言語と文化が陸続きで混在・共存する世界。他民族を「バルバロイ」つまり「わけの分からない言葉を話す者」と呼んだり、バベルの塔の逸話を聖書に記したり、そこにあるのは常に、複数言語の存在が当然という意識だった。聖書自体も翻訳と深い関係にある。早くからヘブライ語、アラム語、ギリシャ語、ラテン語など複数の言語間で当たり前のように翻訳の需要があった。そういう伝統の末にあるのが、23言語を公用語とする現在のEUなのだ。
そういう言語文化世界だからこそ、ライプニッツやデカルトの時代から普遍言語という概念が生まれ、エスペラントに代表される人工言語が考案された。そうした土壌があれば、20世紀早々から機械翻訳という発想が芽ばえたのは、当然と言えるだろう(このくだりは、『機械翻訳』第4章に詳しい)。
一方の日本は、江戸末期から今日に至るまで一貫して、堂々たる"翻訳大国"だ。だが、そこで行われてきた翻訳のほとんどは「他言語から日本語へ」、なかでも「英語から日本語へ」の翻訳だった。つまりターゲット言語は常に日本語であり、考えるべきはソース言語の特性とターゲット言語の特性だけでよかった。
しかも、翻訳という営みは、伝統的に属人的なものと捉えられている。翻訳は個々人の職人技というわけで、翻訳ものは「誰々訳の何々」と語られることが多い(翻訳者・翻訳家の地位が決して低くないのは、こういう背景のおかげでもある)。文芸(出版)翻訳と産業翻訳は区別して考えなければいけないが、前者の文化が後者に大きく影響している面はあるだろう。
ご存じのように、機械翻訳や、それに先だって広がった翻訳支援ツールは、産業翻訳の現場でさえblack sheep扱いだ。実はその根底には、ヨーロッパと日本に存在する上述のような「翻訳観」の違いがあるのではないか―『機械翻訳』を訳してからそう考えることが多くなった。思い切りざっくり言うと、ヨーロッパ的な翻訳観がめざすのは、必要に迫られた「量産のための翻訳」つまり「誰がやっても一定以上の品質になる翻訳」であり、かたや日本的な翻訳観の中心にあるのは、その属人性に基づく「一点物の翻訳」なのだ。
一点物というとまるで文芸翻訳の話のようだが、そうではない。産業翻訳にも一点物の翻訳はある。また、成果物の性質としては量産的であっても、翻訳者ひとりひとりは一点物という意識で翻訳に臨むことが多く、だからこそ産業翻訳の品質が一定以上に保たれていると言える。もちろん、ヨーロッパにも一点物の翻訳は存在するが、産業翻訳との線引きがはっきりしているように感じる。逆に日本では、産業翻訳が文芸翻訳から独立しきっていないのだろうか。
同業者と話をしていても、一点物の翻訳(という意識)を主とする方々と、量産的な翻訳を日常的に扱っている方とでは、機械翻訳の話が基本的にかみ合わないことが多い。もちろん、どちらがいい悪いという話ではなく、翻訳に対するスタンスの違いだ。機械翻訳や翻訳支援ツールが、量産的な翻訳を対象にしているということが、実はいまだに共通認識になっていないと感じることも少なくない。レベルの違いということではなく、一点物の翻訳と量産的な翻訳との違いは意識しておいたほうが、話が進みやすいのではないか。
● 機械翻訳はどこへいくのか?
このフレーズにだけは、若干の違和感がある。「~はどこへいく」という自動詞表現ではなく、「~をどこへ向かわせるのか」という他動的な問いかけであるべきではないか。つまり、関係者一同が機械翻訳の扱い方と方向性を主体的に考え、変えていくべきではないかと思うからだ。個人的には、主に以下のように考えている。
・機械翻訳研究者と翻訳者との協力態勢
ここをもっと深めれば、双方にとって利は大きいはず。その意味では、私のような個人翻訳者が、中澤先生や山田先生たちと多少近しく接しているのは、いい傾向と言えるかもしれない。こういう形をもっと広げていきたい。
・ソリューションの活用に関するガイドライン
機械翻訳が、社会一般でも悪者になってしまう事例が後を絶たない。言うまでもなく、官公庁などで機械翻訳が誤って使われるケースだ。販売者もソリューション導入の時点でもっと指導すべきだが、事例が官公庁で目立つ現状を考えると、機械翻訳の使い方についてのガイドラインが早急に必要だろう。ここはJTFやAAMTの出番ではないか。
・個人翻訳者が機械翻訳を正しく評価できる場
Google翻訳の結果を見て笑うのは、翻訳者としてはあまり建設的ではない。いつまでも「できないところ」を見ているのではなく、「できる」ところを研究・評価しておくべきだ。機械翻訳とどう付き合うかという個々人の判断は、その先にある。