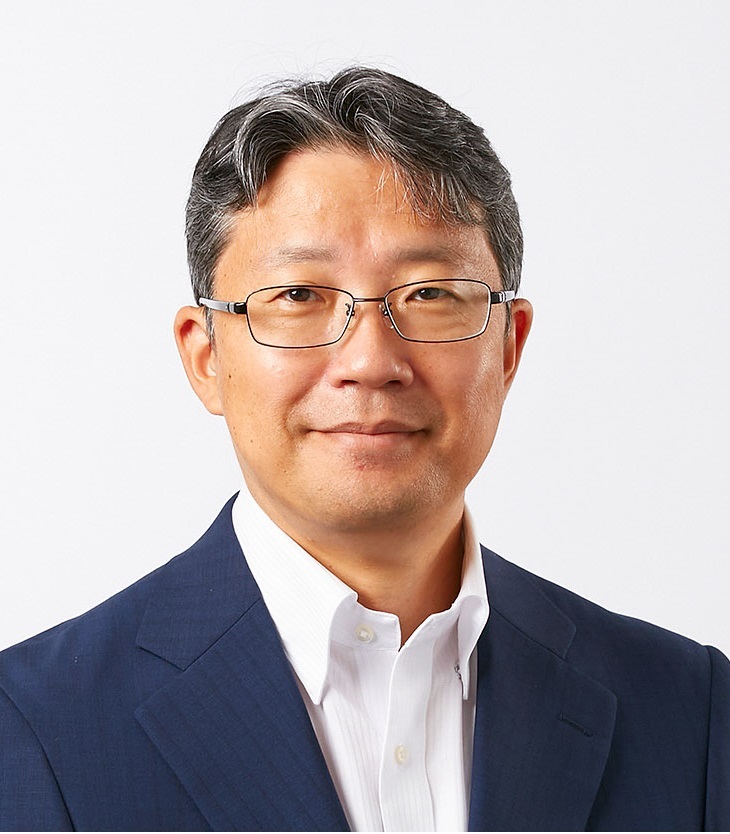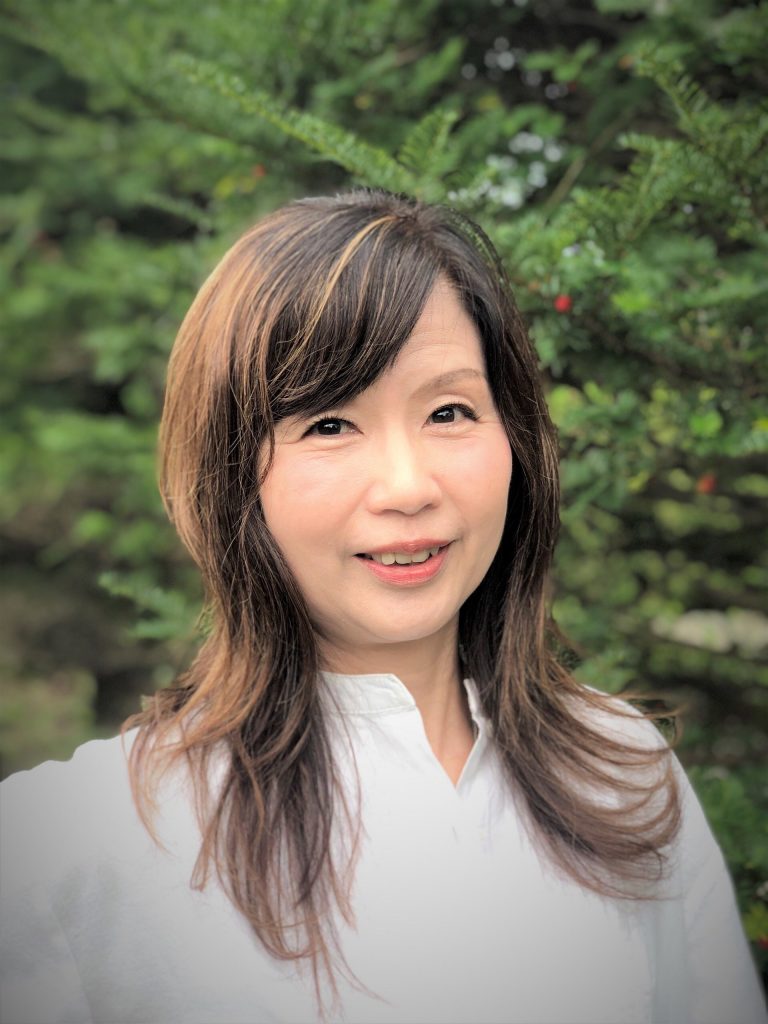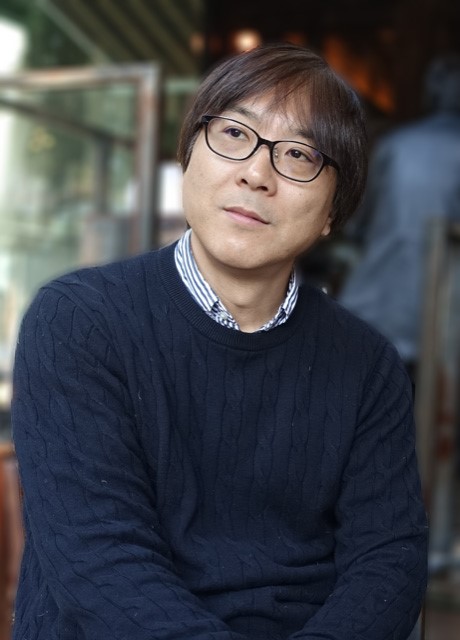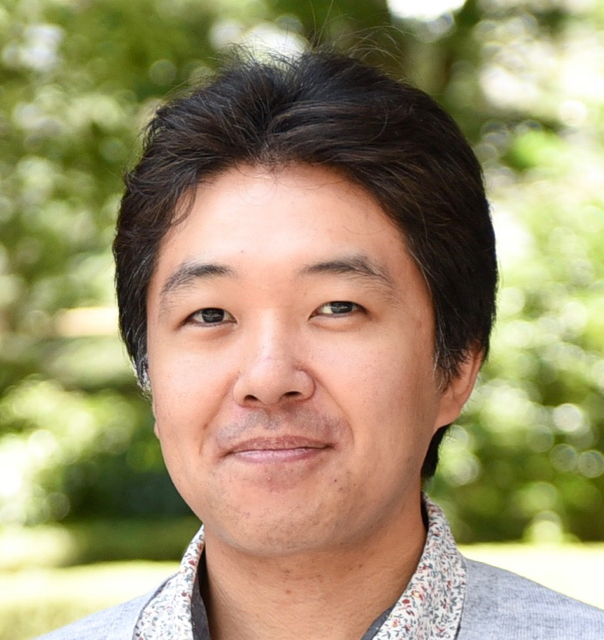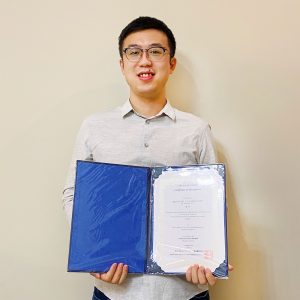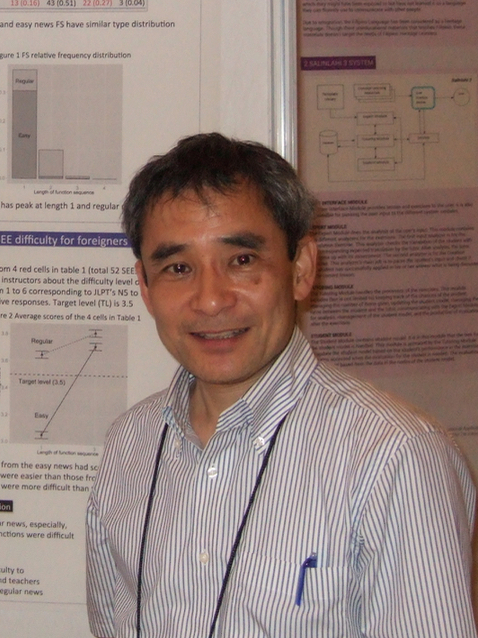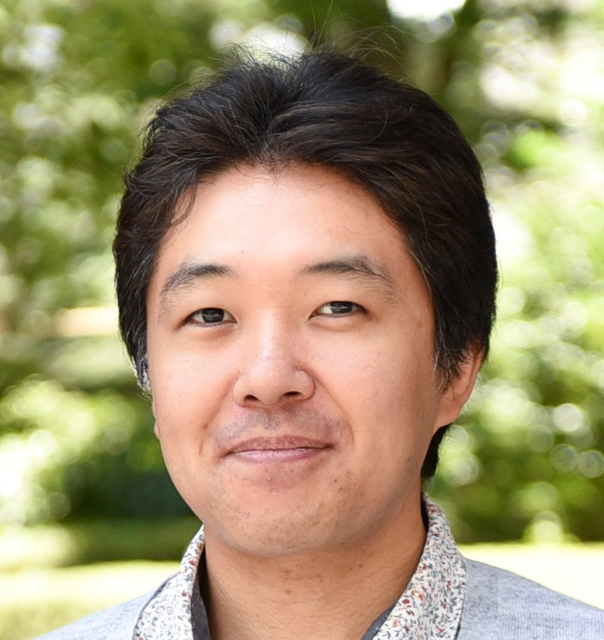人間の翻訳と機械の翻訳(5):翻訳者のコンピテンスとは何か
影浦峡
東京大学・大学院教育学研究科
1. これまでのまとめと今回の話題
本連載では、第1回から第3回で、翻訳の対象、翻訳の対象である文書の性質、翻訳のプロセスについて論じました。第4回(前回)は少し趣向を変え、機械翻訳研究で語られている翻訳と翻訳論で語られている翻訳を計量書誌学的な観点から対比し、機械翻訳研究で捕らえられている翻訳の範囲を観察しました。
今回は、翻訳者のコンピテンスについて考えます[1]。話を始める前に、コンピテンス、そして関連する「知識」「スキル」の定義を与えておきます[2]。
知識:学習により情報を消化して得られるもの。
スキル:タスクの遂行や問題解決のために知識を適用しノウハウを活用する能力。
コンピテンス:仕事や学習の場で、また、専門性の開発や自己の啓発において、知識やスキル、個人的・社会的および/あるいは方法論的能力を使うための、確認された能力
スキルが知識を使う能力であるのに対し、コンピテンスはさらに知識やスキルを使う能力として、一段高次のレベルで定義されていることがわかります。この区別は重要ですが、本稿の前半では、あまり定義にはこだわらず、ゆるやかに考えます。実際のところ、スキルとコンピテンスをはっきりと区別していない議論もありますし、また、どのようなコンピテンスが必要かをめぐる議論の展開を追う場合、時期によってコンピテンスの定義が同一でないこともあるからです。とはいえ、具体的な作業に対応して必要な知識、スキル、コンピテンスを定義し、MTがカバーしているのは知識なのかスキルなのかコンピテンスと言えるものなのかを検討する作業は、理論的に重要です。後半では少しそのことを意識します。
2. 翻訳コンピテンス論の展開
翻訳のスキルやコンピテンスをめぐる議論が盛んになった1970年代からの展開を簡単に追います[3]。
Wilss (1976)は、翻訳コンピテンス涵養の重要性を説き、そのコンピテンスを「技術的なテキスト、一般的なテキスト、文学テキストを目標言語で十分なかたちで再生産する能力」とし、そのために「起点言語と目標言語において文法、語、形態素の包括的な知識を有するだけでなく、起点言語と目標言語のテキスト世界に関する完全なスタイル上(テキスト上)の知識を必要とする」と述べています[4]。House (1980)は、翻訳コンピテンスを「読み、書き、聞き取り、話すことに加えて第5の基本的な言語スキル」と述べています[5]。
これらに対してKiraly (1995)は、「翻訳コンピテンスではなく翻訳者コンピテンス」を翻訳教育の目標とすべきとし、この「用語を選ぶことで、プロ翻訳者のタスクが有する複雑な性格と、必要とされる非言語的スキルを強調する」ことができると述べています[5]。その後、コンピテンスといっても曖昧なままではないか、といった批判を経て[6]、コンピテンスのカテゴリが列挙されるようになります。
例えば、Kelly (2005)は、(a) コミュニケーションとテキストに関するコンピテンス、(b) 文化および間文化に関するコンピテンス、(c) 主題分野に関するコンピテンス、(d) 専門性および道具に関するコンピテンス、 (e) 態度と心理=生理的側面に関するコンピテンス、 (f) 対人関係に関するコンピテンス、(g) 戦略に関するコンピテンス、という7種類のコンピテンス・カテゴリを挙げています[7]。
Wilss (1976)やHouse (1980)と比べると、コンピテンスの範囲が広くなっていることがはっきりとわかります。もちろんこれだけでは相変わらず、「で、結局、それはどういうもの?」という疑問が湧きますが、この点についても、翻訳教育や翻訳論のそれ以外のところで、一定程度、外在的な操作の手続きとして共有可能な具体性をもったかたちでコンピテンスを記述する試みは続いてきました。コンピテンスの定義が「確認された能力」であり、この「確認」は自己の内面報告ではあり得ないことを考えると、翻訳論におけるコンピテンスを巡る議論は、十分かどうかは別にして、(1)翻訳の実態を反映し言語力以外に必要なコンピテンスを考慮する、(2) 具体的に共有可能な解像度での記述を目指す、という、適切な方向に向かってきたと言えるでしょう[8]。
3. ISO 17100とEMT 2017
ISO (2015)は、翻訳者に求められるコンピテンスとして、以下の6つを挙げています[9]。
- 翻訳コンピテンス [この規格に従って]内容を翻訳する能力で、言語コンテンツの理解と生成、クライアントと翻訳サービスプロバイダ(TSP)の取り決めをはじめとする翻訳の仕様に従って目標言語コンテンツを提供する能力を含む。
- 起点言語と目標言語における言語とテキストに関するコンピテンス 起点言語を理解する能力、目標言語の流暢さ、テキストタイプの約束事をめぐる知識。それを適用する能力を含む。
- 調査、情報の収集と処理に関するコンピテンス 起点言語コンテンツ理解や目標言語コンテンツ生成に必要な知識を効率的に入手する能力。ツールの利用や情報源の利用方法に関する能力を含む。
- 文化に関するコンピテンス 行動規範、用語法、価値体系、ロケールに関する情報を利用する能力。
- 技術に関するコンピテンス ツールやITシステム等を用いて必要な技術的タスクを遂行する力。
- 分野に関するコンピテンス 起点言語文書のコンテンツを理解し、適切なスタイルと用語を使って目標言語を生成する能力。
a)の「この規格に従って」のところは、原文では「翻訳」を定めた項が具体的に参照されています[10]。そこでは、翻訳プロジェクトの目的に則して翻訳することと総論が書かれた上で、その際に、分野やクライアントの用語集等に従い一貫させること、意味の正確さを維持すること、適切な文法や句読法、正書法上の約束事に従うこと、表現の結束性や適切な言い回しを用いること、定められたスタイルガイドに従うこと、ロケール等基準に従うこと、適切なフォーマットを用いること、想定読者と翻訳目的に適したものにすること、が書かれています。
EMT (2017)は欧州共通翻訳修士枠組みにおけるコンピテンスの枠組みを定めたもので、ISO (2015)のa)-c)が「翻訳」の方略と方法に関するコンピテンス、f)が「翻訳」のテーマに関するコンピテンスと、分類が少し違いますが、大枠としては対応したコンピテンスが挙げられています[11]。他に人的・対人的なコンピテンス、サービス提供が挙げられています。教育の観点からこれらを含めるのは自然なことでしょう。
ISO (2015)もEMT (2017)も、コンピテンスを「言語的」なものとして(だけ)ではないものと捉えています。本連載第1回でも紹介しましたが、EMT (2017)は、少なくとも二つの言語の十分な力は、翻訳を学ぶための前提条件であると述べています。
4. 実証的観察から:調査のコンピテンス
ここでは、調査のコンピテンスに絞り、Onishi and Yamada (2020; 2021)の研究の一部を紹介します[12]。英日翻訳において、英語専攻の学生5名(翻訳授業の履修経験有)とプロの翻訳者4名を対象に、翻訳作業時の情報探索(調査)行動を量的・質的に分析したもので、次のようなことが観察されています。
- 翻訳にかける時間はプロの翻訳者の方が長く、その差の大部分は情報探索に要した時間である。
- プロの翻訳者は辞書の検索よりも辞書以外の検索に費やす時間がはるかに長いが学生は同じくらいの時間を費やす。辞書以外の情報探索が良質の翻訳を作る鍵でありそうである。
- 目標言語の表現を検索する回数はプロの翻訳者が有意に多い。
- 検索エンジン結果からのジャンプ数はプロの翻訳者の方が多い傾向がある。
- プロ翻訳者は文書を理解するために下調べを行うが学生ではそうした意識は薄い。
全体の傾向として、学生が「言語」についての探索を行なっているのに対して、プロの翻訳者は文書の内容をめぐる探索を行なっていると言えそうです。このことは、翻訳が言語に関する行為ではなく文書に関する行為であることとよく対応しています。
この結果は、翻訳者の翻訳行動に広く一般化することはできません。例えば、特定領域・タイプの文書を専門に扱うプロの翻訳者は調査をほとんど必要としないことがあります。けれども、調査を要する翻訳タスクにおいて、良質の目標言語を作るためにプロの翻訳者がどのような行動を取るかについては、特徴を良く示しています。情報探索の能力が高い翻訳者の翻訳品質が高いことを示す研究もあります[13]。
5. コンピテンスの運用・運用のコンピテンス
ここまで、翻訳者に求められるコンピテンスについて枠組みと一部の実証結果を示してきました。実は、コンピテンスについては、概念的に少し曖昧なところが残っています。冒頭で挙げたコンピテンスの定義は「知識やスキル、・・・能力を使う・・・能力」となっています。ところが2節と3節でまとめたコンピテンスのカテゴリや枠組みは、基本的に、「知識やスキル、・・・能力」そのものです(ISOのb)に「それを適用する能力を含む」とありますが、これも、適用の判断を指しているのか個々の適用のスキルを指しているのかははっきりしません)。
4節で見たプロの翻訳者と学生の翻訳者の違いは、単に言語レベルでの原文の理解力(それが何を意味するかについてここでは立ち入りませんが)や情報探索スキルの差だけを示しているのではなく、そもそも、どのようなときに情報探索を行う必要があるかをめぐる判断に関する差異を反映しています。誤訳は、起点言語文書がわからないときにではなく、わかっていないことを意識できないときに生まれます。トップレベルのプロの翻訳者に「なんとなく変だぞ」と感じる力があることはよく言われることです。
知識やスキルや能力を運用する力を運用のコンピテンスと呼ぶことにしましょう。冒頭のコンピテンスの定義は、第一義的には運用のコンピテンスを示しています。そうであるなら、「なんとなく変だぞ」のセンスは、コンピテンスの核にあると考えられます。
ここで運用のコンピテンスが問題になるのは、与えられた起点言語文書を前にしたとき、それを翻訳するために、既に有している知識やスキルを一般的に適用するだけでは十分ではないからです。敷衍しましょう。
第一に、3節のISO (2015)の紹介で述べたように、翻訳においては、(プロジェクト毎に)その都度、そこで定義された目的や条件、使用すべき用語集や句読法・正書法の規定等に従って訳出する必要があります。母語話者にとっては簡単なことと思われるかもしれませんが、学生のレポートを見るとそう簡単ではないことがわかりますし、大学教員でも、それを十分にできるわけでは必ずしもありません[14]。
第二に、本連載第1回で、言語処理には「知識がないとどうにも解けない問題がいっぱいある」という工藤拓さんの言葉を引用しましたが[15]、本質的に「言語処理」ではない翻訳では、知識があってもどうにもならなくて、というのも、与えられた文書を理解する必要があり、そこでは既往の知識を適用するのではなく知識を構築していく作業を伴い、それは知識の不足ではなく文書を理解するということに必然的なことなので、すなわち、理念的に文書というものはそれを適用することで理解できる知識が事前に定義できないようなかたちであり、現実にもそのような文書は少なからずあって、翻訳者はそれに対応しなくてはならない、そのため、知識やスキルを身に付けていることは前提として、その都度、文書の理解に必要な知識を構築するために知識やスキルを発動する運用のコンピテンスが問われる、ということになります。
多少強引に「科学とは専門家の無知を信じることだ」というファインマンの言葉を借りると[16]、翻訳者は文書を前に自ら専門家だから専門家として自らの知識を適用することで翻訳ができるという前提ではなく、自らの無知を踏まえて翻訳に臨むという点で、未知の事象を前にした科学者に似ていると言えます。
少し話がずれますが、翻訳が完成するというのも不思議なもので、(工程としては定義できるとしても)理論的にはどこで終了にしてよいのかよくわかりませんが、でも何故かしら、翻訳は一応、終わります。
6. おわりに
少しMTを意識してまとめます。第一に興味深いのは、翻訳者のコンピテンスをめぐる議論がコンピテンスを外在化して認識する方向に発展してきたことで、一般にこれは、民主的な共有、さらに機械化の方向なのですが、NMTの成功はむしろ処理のブラックボックス化と対応していること。NMTの出力が翻訳をよく知らないけれど言葉はある程度できる学生の訳に似ていることは、これに対応しています。MTの観点からは、スキル的なものとして翻訳者のコンピテンスのうちどの範囲がMTで扱われ、どの程度の能力を持っているかを、技術的な問題として操作可能性を維持した解像度で考えるのは重要な課題になるでしょう。
もう一つは、それぞれの文書に応じたその場での情報探索と理解と選択と決定が翻訳者のコンピテンスの中核にあることが示されたのに対し、これに対応する機構をMTは持っていないことで、喩えて言うとMTは事前の知識を適用することだけで全てを行おうとし、その都度、文書を未知のものとして理解しようとする科学的な態度を取れない、専門家のような存在です。分野適応をしたとしてもその分野の専門家になるに過ぎず、文書を前にした科学的態度をエミュレートできるわけではありません(技術においてそうしなくてはならないことは必ずしもないのですが)。
だから文書をその都度理解できる人間はすばらしいと言うことほど非科学的な態度もないので、ではどうすればよいかを問う必要があります。大きく二つの方向性がありそうです。第一は、MTの出力は翻訳結果ではないとすること。MTPEの研究はその方向を向いています。第二は、MTに翻訳者のコンピテンスに対応するコンピテンスを持たせること。品質推定(QE)が人間の翻訳の評価に対応するならば、与えられた文書に対するQEを起点にしてその文書の翻訳に必要な情報探索や学習を発動させる手法を考えることは、誰もが思いつく出発点の一つです。
ところで、「これで翻訳終了」の判断はどうすればよいのでしょうか。これは、人間にもわかっていません。MTが鳥のようにではなく飛ぶ飛行機のように実現できる可能性は、翻訳の全体が人間における行為としてしか定義されないことを考えると、あまり大きくはなさそうです。なので、MTが翻訳できるようになるために、翻訳についてまだ解明しなくてはならないところが、それを「解明」するとはどういうことかも含め、かなり残っていると考えるのが妥当なようです。
7. 謝辞
翻訳・翻訳者のコンピテンスの整理は、朴惠氏と山田優氏(と)の研究(具体的な情報は「注・参考文献」に記載)に依拠しています。両氏に感謝します。本記事の一部は、科研研究費基盤(S)「翻訳規範とコンピテンスの可操作化を通した翻訳プロセス・モデルと統合環境の構築」(19H05660)に関わっています。